一分の救い(ノンフィクション風の物語)⑬
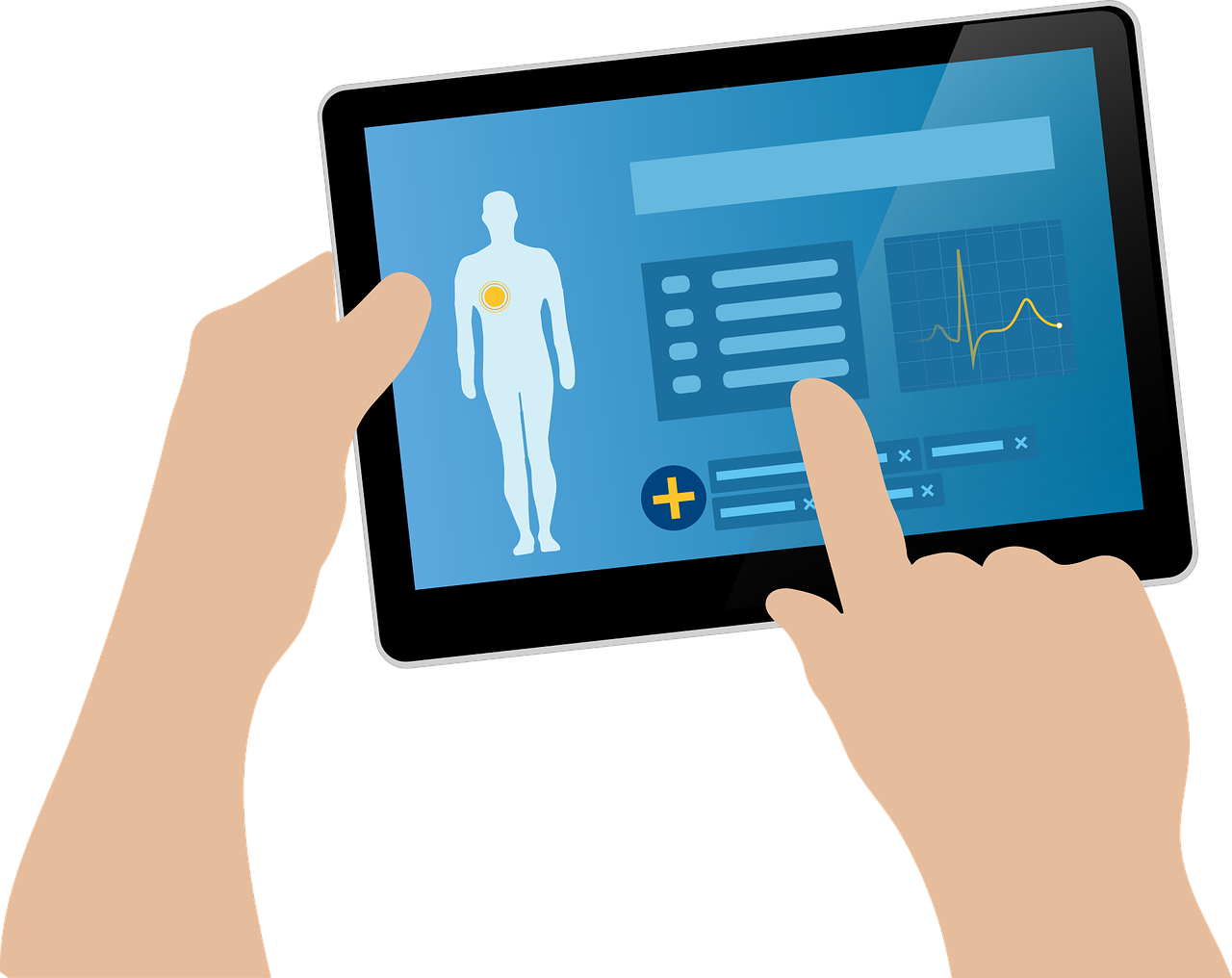
病状が快方へ向かうと、その患者のまわりの空気は一変する。
家族のみならず、医師や看護師も余裕を持って接するようになる。
また、少しでも平常の生活に戻すために前向きの行動が増えてくる。
このことは、何よりも母や家族を元気づけた。
「今日は車椅子で玄関をでて空をみてきた」
「30m歩いてもへっちゃらだった」
「トイレがひとりでできるようになった」
母の報告は嬉しいものばかりだった。
家族も生活を取り戻していく。
つきっきりで病院にいる必要がなくなった。
そして、母も重症患者の病室から一般の病室へ移動することができた。
さすがに発病前と同じ生活に戻ることは難しいとしても、あきらめかけていた「帰宅」に関しては望みをもてるようになってきた。
母も看護師にそれを告げることがあったらしい。
そして、母のリハビリが始まった。
リハビリとは、廊下をよちよち歩くのではなく、リハビリセンターへ移動してトレーニングをするということである。
母は、病院の指示に何ら疑問を持つことなくリハビリにいそしんでいた。
しかし、、、
私は、これには大きな危惧があると感じていた。
肝硬変を患っている患者は、肝臓に流れ込む血液の流れが悪いために、食道や胃の静脈がもろくなり、静脈瘤(血管の表面が凸凹になり風船が膨らんでいる感じになる)を生じさせる。
また、出血傾向(血が止まりにくい)状態にあることも特徴で、何かのきっかけでこの静脈瘤が破裂した場合、たいへん危険な状態になることがあるのだ。
事実、肝硬変患者の最期は静脈瘤破裂によることも多い。
母も検査の結果、食道静脈瘤が発見されていたし、1年も手術の傷が塞がらなかったことからも出血傾向にあることも否めない。
そして、なによりも負荷のかかる運動は健康体でも血液を溶けやすい方向に傾けさせることがわかっている。
このことから、内科的、運動生理学的な専門知識の乏しいリハビリセンターの療法士に運動を任せることへの不安があったのである。
なので、私は「少しでも無理だと感じたらリハビリを中止するように自分から申し出るように」とアドバイスをしていた。
しかし、前述したように、時は昭和・・・。
セカンドオピニオンもない時代に「お医者様」のいうことに母が意義を唱えるはずはなかった。
まあ見ようによっては無理もない。
1年間も腹水でお腹を膨らませて管の抜けなかった母がスクワットをするというのは、おそらく現場では感動的な出来事で、母もやりがいのあるリハビリだったに違いないからである。
ただ、食道静脈瘤破裂は「ちょっと疲れた」とか「少し休めば」とかではないダイレクトに命に関わる緊急事態を惹き起こす。
私も口を酸っぱくして警告し続けたが、日に日に体力がついていく母を見ることも嬉しいことにことに違いはなかった。
「何とかこのまま日常生活レベルに達してくれ」
と願っていたが、ついにその日は突然訪れた。
(つづく)